長い道のりを共にしてきた鎌足の死を悼み、天智天皇はこれまでの想いや鎌足への願いを言葉にする。
(三五)
天智天皇二年(669年)十月十六日、鎌足は淡海の屋敷で息を引き取った。享年五十六であった。天皇は声を上げて泣き、ひどく悲しまれた。それは彼の死を悼んで、政を九日も休まれたほどであった。
十九日、天皇は宗我舎人臣を遣わし、詔を述べられた。
内大臣某朝臣(鎌足)は、前触れもなく突然亡くなってしまった。天は何故大切な君子を奪ってしまわれたのか。辛く悲しいことだ。彼は私を置いて遠くへ行ってしまった。不思議で残念なことだ。私に背き、永遠に離れてしまったのだ。何をもって別れの言葉とし、何をもって惜別の言葉としよう。これは嘘偽りのない、私の真なる言葉なのである。
公(鎌足)とは昼も夜も手を取り合う仲であり、常に傍に置き、時に勅使とし、おかげで私の心は安らかだった。鎌足の言うことなすこと全てを疑うことがなかった。国にかかわることは、小さな事も大きな事もいつも共に決めてきた。その結果、天下安寧を成し、民の愁いもなかったのだ。
以上を贈る言葉としたいが、彼に捧げるには言葉が貧しく足りない。一体どうやってこの心を伝えれば良いのだろう。
(三六)
鎌足が己の考えを進言すればおのずから民の利となり、政について議論すれば必ず私の考えと一致した。鎌足との出会いはまさに奇跡だったのだ。周の文王は太公望を大臣とし、漢の高祖は張良を得たが、どうして私と鎌足の仲と比べられよう。
朝から晩まで手を取り合い、どれだけ仲を深めても飽きることはなかった。宮に入る時は同じ車に乗り、外へ出ても互いに礼を尽くした。
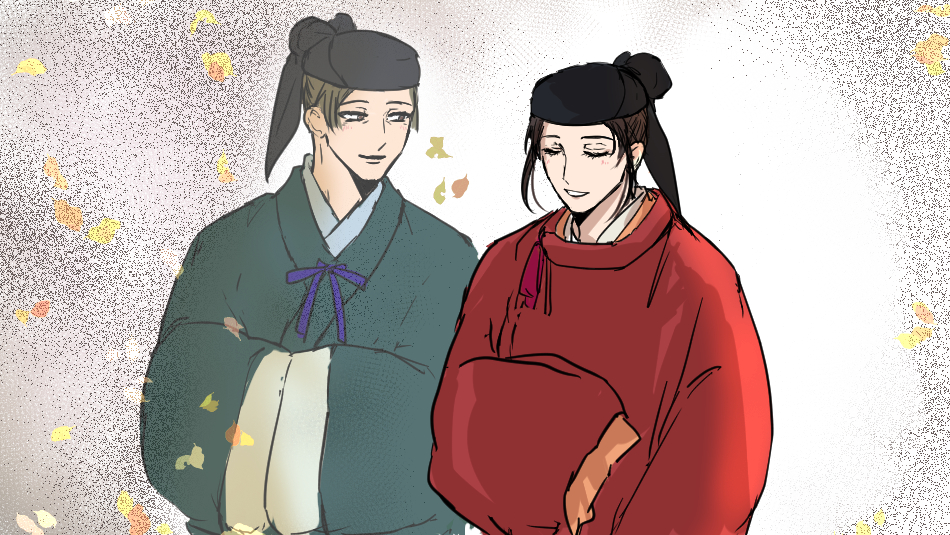
大いなる目的を未だ果たしておらぬのに、国の舟であり揖ともなる男は亡くなってしまったのだ。国の礎を築き始めたばかりであるのに、国の棟であり梁ともなる鎌足は亡くなってしまったのだ。私は一体これから誰と共に国を治め、誰と共に民を統べれば良いのだろう。これを思う度に、無念な心が深まるばかりである。
悟りを開いた聖人でさえ、死を免れることは出来ぬという。この言葉で痛む哀しみを少しでも慰め、心の安寧を得ることが出来た。
(三七)
もし鎌足の魂が在り、先帝(舒明)と皇后(皇極・斉明)に謁見できるのであれば、「先帝がいつも遊覧に出ておられた琵琶湖と平良の浦の都は、今も尚あの日のまま穏やかだ」と伝えておくれ。私はこの景色を目にする度、遠く里の景色を眺め、心を痛めぬ時はなかった。先帝や皇后の一挙手一投足、一つの言葉も残さず覚えている。天を仰いでは彼らの聖徳を望み、地に伏しては彼らへの思慕を深くしている。
加えて、鎌足が出家して仏教に帰依するのならば必ず法具が必要だろう。純金の香炉をお前に捧げよう。この香炉を持ち、望み通り観音菩薩に従って兜率陀天へ行き、昼も夜も観音菩薩の妙説を聞き、朝から晩まで真如の教えを周囲に説くと良い──と。
挿絵:雷万郎
文章:あめ
藤氏家伝「鎌足伝(14)」登場人物紹介
〈天智天皇〉
中大兄皇子としても知られる。虚しくも亡くなってしまった鎌足に追悼の言葉を述べる。
〈中臣鎌足〉
天智天皇の右腕。病によって亡くなってしまった。
