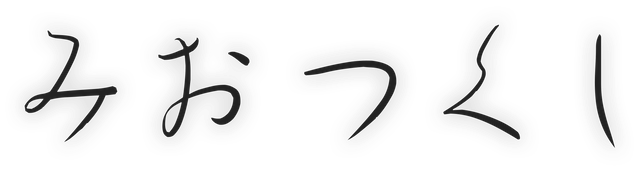祝!大宝律令施行!ついに古代日本国家の悲願、大宝律令が完成したよ!新しい官位制度もできたし、遣唐使も派遣されるし、年号も変わるし、おめでたい!そしてこの年、新時代の申し子がついに爆誕……?!次回もお楽しみに?!
大宝元年(701年)
春正月一日 天皇は大極殿に出御して朝賀を受けた。その儀は正門において烏形の幡を立てて、左側には日像の青龍・朱雀の幡、右側には月像の玄武・白虎の幡を立てた。蛮夷の使者も列して左右に並んだ。文物の儀はここにおいて整った。
正月四日 天皇は大安殿に出御して祥瑞を受けた。これは告朔の儀式と同じようだった。
正月十四日 新羅の大使、薩飡の金所毛が卒した。絁百五十疋、真綿九百三十二斤、麻布百段を贈って弔った。少使で級飡の金順慶と水手以上の者には身分に応じて物を賜った。
正月十五日 大納言で正広参の大伴宿禰御行が薨じた。天皇は死を甚だ悼み惜しんで、直広肆の榎井連倭麻呂らを遣わして葬儀を監護させた。直広壱の藤原朝臣不比等らを邸に遣わして詔を告げさせ、正広弍の位と右大臣の官を追贈された。御行は難波朝の右大臣で、大紫の位の長徳の子である。
正月十六日 皇親と百官に朝堂において宴を賜った。直広弍以上の者には特に御器の膳(天皇と同じ器の食事)と、衣・裳を授け歓楽を尽くして終わった。
正月十八日 大射の礼を取りやめた。贈右大臣(御行)の喪中のためである。
正月二十三日 民部尚書で直広弍の粟田朝臣真人を遣唐執節使に任命した。左大弁で直広参の高橋朝臣笠間を遣唐大使とし、右兵衛率で直広肆の坂合部宿禰大分を副使とし、参河守で務大肆の許勢朝臣祖大位とし、刑部判事で進大壱の鴨朝臣吉備麻呂を中位、山代国相楽郡令で追広い肆の掃守宿禰阿賀留を少位とし、進大参の錦部連道麻呂を大録とし、進大肆の白猪史阿麻留・無位の山於憶良を少録とした。
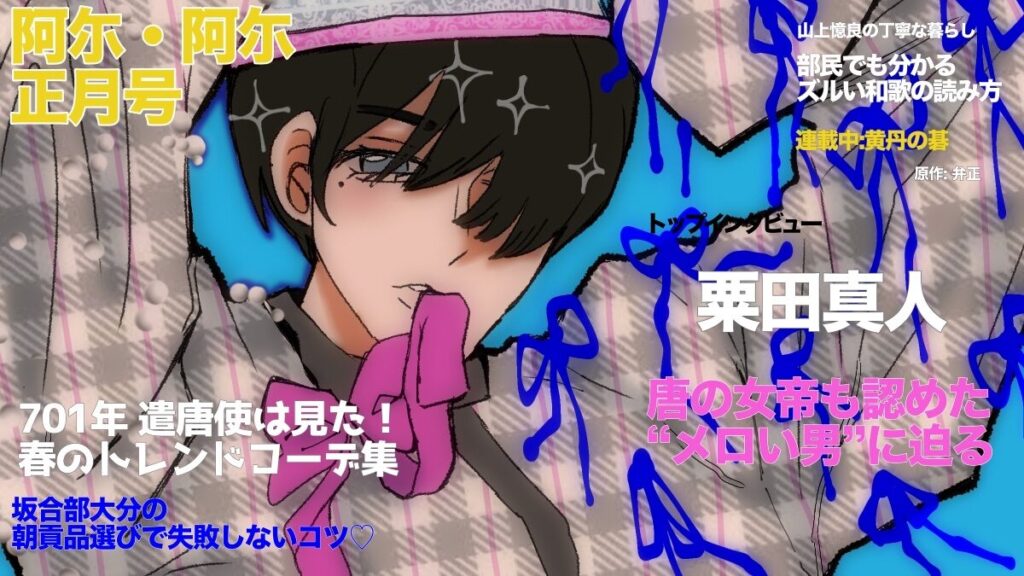
正月二十九日 直広壱の縣犬養宿禰大侶が卒した。浄広肆の夜気王らをその邸に遣わして詔を告げさせ、正広参の位を追贈された。壬申の乱の時の功績のためである。
二月四日 詔して初めて下物職を任命した。
二月十四日 釈奠(釈奠の礼ここに於いて初めて記録が見える)を行った。
二月十六日 泉内親王を遣わして、伊勢の斎宮に侍らせた。
二月二十日 吉野離宮に行幸された。
二月二十三日 民官の戸籍を管理する史らを任命した。
二月二十七日 天皇が吉野から還られた。
三月三日 王親や群臣に東安殿において宴を賜った。
三月十五日 追大肆の凡海宿禰麁鎌を陸奥に遣わして金の精錬をさせた。
三月十九日 僧の弁紀を還俗させて代わりに一人を出家させた。弁紀に春日倉首という姓と老という名前を与え、追大壱の位を授けた。
三月二十一日 対馬嶋が金を貢じた。そこで新しく元号をたてて大宝元年とした。初めて新令に基づいて官名と位号の制を改正した。
親王に与える明冠は一品より四品までの四階、諸王に与える浄冠は正一位より従五位下までの十四階、合わせて十八階とし、諸臣に与える正冠は正一位より従三位までの六階、直冠は正四位上より従五位下までの八階、勤冠は正六位上より従六位下までの四階、務冠は正七位上より従七位下までの四階、追冠は正八位上より従八位下までの四階、進冠は大初位上より少初位下までの四階、合計三十階である。
外位は直冠の正五位上の位階より始まり進冠の少初位下の位階に終わるまで、合計二十階。勲位は勲一等が正冠の正三位の位階より始まり、勲十二等が追冠の従八位下の位階で終わるまで合わせて十二等である。そこで官人には冠を授けることをやめて代わりに位記を授けることとした。詳しくは年代暦にある。
また服装を定め、親王の四品以上と諸王・諸臣の一位の者はみな黒紫色、諸王の二位以下と諸臣の三位以上の者はみな赤紫色、直冠の上位四階の者は深緋色、直冠の下位四階は浅緋色、勤冠の四冠は深緑色、務冠の四階は浅緑色、追冠の四階は深縹色、進冠の四階は浅縹色とし、みなそれぞれ漆の冠、綺(薄い絹織物)の帯、白色の襪(足袋)、黒革の舃(爪先をそらした儀式用の沓)、その袴は直冠以上のものは皆白色の縛ロ袴、勤冠
以下の者は白色の脛裳とする。
左大臣で正広弐の多治比真人嶋に正冠の正二位、大納言で正広参の阿倍朝臣御主人に正冠の従二位、中納言で直大壱の石上朝臣麻呂と直広壱の藤原朝臣不比等に正冠の正三位、直大壱の大伴宿禰安麻呂と直広弐の紀朝臣麻呂に正冠の従三位を授けた。また諸王十四人と諸臣百五人についてはそれぞれの位号を改め、地位に応じて位階を昇進させた。
大納言で正冠従二位の阿倍朝臣御主人を右大臣に任じ、中納言で正冠正三位の石上朝臣麻呂・藤原朝臣不比等・正冠従三位の紀朝臣麻呂をともに大納言に任じた。大宝令の発足でこの日、中納言の官職を廃止した。
三月二十六日 丹波国で三日間地震が続いた。
三月二十九日 右大臣・従二位の阿倍朝臣御主人に、絁五百疋、絹糸四百絇、麻布五千段、鍬一万口、鉄五万斤と備前・備中・但馬・安芸の諸国の田二十町を授けた。
夏四月一日 日蝕があった。
四月三日 次のように勅した。
山背国葛野郡の月読神・樺井神・木嶋神・波都賀志神などの神稲については今後は中臣氏に給付せよ。
四月七日 右大弁・従四位下の下毛野朝臣古麻呂ら三人を遣わし、初めて新令を講釈された。親王・諸王・諸臣をはじめ諸官の人たちは古麻呂らについて学習した。
四月十日 遣唐大通事の大津造広人に垂水君という姓を与えた。
四月十二日 遣唐使らが天皇に拝謁した。
四月十五日 幣帛を諸社に奉納して、名山大川に雨乞いをした。田領を廃止し、その仕事を国司の巡検に委ねた。
五月一日 太政官は次のように処分を下した。
五月五日 群臣の五位以上に端午の節句に行う騎射の走馬を出させた。天皇は臨席してそれをご覧になった。
五月七日 入唐使の粟田朝臣真人に節刀を授けた。天皇は次のように勅した。
一位以下の官人も休暇を賜うのじゃ十五日を越えることはできない。ただし大納言以上の職にあるものは責任が重いのでこの限りに入らない。
五月二十七日 初めて勤冠以下の位号を改正した。これと同時に、内官・外官とも六位以下の有位の者に位階一級を昇進させた。
六月一日 正七位下の下道君首名に命じて大安寺で僧尼令を講説させた。
六月二日 正五位上の忌部宿禰色布知が卒した。天皇は詔して従四位上を追贈された。壬申の乱の功績のためである。
この度初めて内舎人九十人を任命し、太政官において整列・謁見を行った。
六月八日 次のように勅された。
全ての官庁の諸務は専ら新令に準拠して行うようにせよ。また国司や郡司が大税を貯えておくことについては必ず法規の通りにせよ。若し過失や怠慢があれば事情に随って処罰せよ。
この日、使者を七道に派遣して、今後新令に基づいて政治を行うことと、また大租が給付される状況を説明し、合わせて新しい国印の見本を頒布した。
六月十一日 正五位上の波多朝臣牟胡閇と従五位上の許曽部朝臣陽麻呂を薬師寺建造の司に任じた。
六月十六日 天皇は王親や側近の臣下を従えて西の高殿で宴を催した。参会者には御器の膳と薄絹が身分に応じて授けられた。
六月二十五日 時節の雨が降らないので、四畿内の国々に命じて雨乞いをさせ、合わせてこの年の調を免除した。
六月二十九日 太上天皇(持統)が吉野離宮に行幸した。
続日本紀「文武天皇(5)」登場人物
<文武天皇>
第42代天皇。父祖代々の悲願をついに達成!えらいぞ涙
<藤原不比等>
大宝律令爆誕の中心メンバーの一人。官位もアップ!ビッグな孫とビッグな娘も生まれてるかも?
<粟田真人>
遣唐執節使。唐で美丈夫と評判に?!