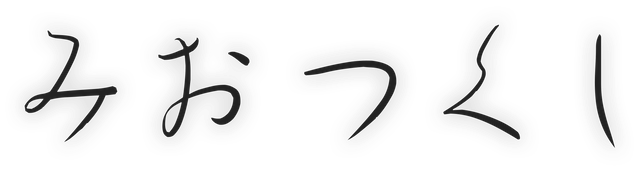天武天皇六年と七年の動静について。
天武天皇五年春正月一日、文武百官が拝朝した。高市皇子以下、小錦以上の大夫たちに衣、袴、褶、腰帯、脚带および、机、杖を賜わった。ただし、小錦の三階には机を賜らなかった。
七日、小錦以上の大夫たちにそれぞれの位に応じて禄を賜った。
十五日、百寮の初位以上が薪を献上した。その日、皆を朝廷に集めて宴を催した。
十六日、西門の庭で弓の試合を行った。的にあたった者にはその成績に応じて禄を賜った。この日、天皇は島宮に出御して宴を開いた。
二十五日、「国司を任命するときは畿内と陸奥、長門国以外は大山位以下の人を任命するように」と詔した。
二月一日、儀礼を行った。
二十四日、耽羅の客人に船一隻を賜った。
この月、大伴連国麻呂らが新羅より帰国した。
夏四月四日、龍田の風神と広瀬の大忌神を祀った。大和国の添下郡の鰐積吉事が瑞鶏を献上した。そのトサカは椿の花に似ていた。この日、大和国の飽波郡が雌鶏が雄鶏になったと報告した。
十四日、「諸王と諸臣に支給する封戸の税は、京以西の国をやめて東国に替えるようにせよ。また、畿内の外の者が宮廷に仕えたいと望む場合は臣連、伴造、および国造の子は許可する。それ以下の庶人であっても、才長けた者は認める」と詔した。
二十二日、美濃の国司に「礪杵郡にいる紀臣訶佐麻呂の子を東国に移して、その国の百姓とするように」と詔した。
五月三日、調の納付期限を過ぎている国司たちの状況を云々と仰った。
七日、下野国の国司が、国内の百姓たちは凶作が原因で飢えて子を売ろうとしていますと奏上したが、朝廷は許さなかった。
この月、南淵山と細川山で草木を切ることを禁じ、また、畿内の山野で以前より草刈り禁止のところではみだりに切ったり焼いたりしてはならない旨を詔した。
六月、四位の栗隈王が病を得て薨じた。物部雄君は急病で卒した。天皇はそれを聞いて大いに驚かれた。あの壬申の年に車駕に従って東国に入り、大功があったことを以て恩を降し、内大紫の位を贈った。そして、氏上の地位を与えた。
この夏、大規模な旱魃が起こった。使いを各地に遣わして、幣帛を捧げて諸神に祈りを捧げた。また、多くの僧尼を招いて三宝に祈らせた。しかし雨は降らなかった。そのせいで作物は実らず、百姓は飢えてしまった。

秋七月二日、文武百官にそれぞれの位に応じて爵位の昇進を行った。
八日、耽羅の客人が帰国した。
十六日、龍田の風神と広瀬の大忌神を祀った。
この月、村国連雄依が卒した。壬申の年の功績によって外小紫の位を贈った。
彗星が東の空に現れた。その長さは七、八尺ほどであった。九月になって大空にかかった。
八月二日、親王以下、小錦以上の大夫、および皇女、姫王、内命婦らにそれぞれの位に応じて食封を賜った。
十六日、「全国で大祓をしよう。用いる供物は、国ごとに国造は馬一匹、布一常、このほかの郡司は郡司はそれぞれ刀一口、鹿皮一張、鑊一口、刀子一口、鎌一口、矢一具、稲一束とし、また家ごとに麻一条を出すように」と詔した。
十七日、「死刑、没官、三種類の配流はいずれも一級ずつ下げ、徒刑以下は、すでに発覚したものもまだ発覚していないものも全て赦免せよ。ただしすでに配流された者については対象外とする」と詔した。この日、諸国に詔して放生を行った。
この月、大三輪真上田子君が卒した。天皇はそれを聞いて大いに悲しみ、壬申の年の功を以て内小紫の位を贈った。また、大三輪真上田迎君との諡号を賜った。
九月一日、雨が降ったので告朔の儀式を行わなかった。
十日、王卿を京および畿内に遣わして、人別に兵器を調べさせた。
十二日、筑紫太宰三位の屋垣王に罪があったので土佐国に流した。
十三日、百寮の人と諸藩の人にそれぞれの位に応じて禄を賜った。
二十一日、「新嘗祭について占いましたところ、斎忌は尾張国山田郡、次は丹波国訶沙郡と出ました」と神官が奏上した。
この月、坂田公雷が卒した。壬申の年の功を以て大紫の位を贈った。
冬十月一日、酒を用意して群臣に宴を賜った。
三日、相新嘗の諸神に幣帛を奉った。
十日、大乙上の物部連麻呂を大使、大乙中の山背直百足を小使として新羅に遣わした。
十一月一日、新嘗祭のために告朔の儀式をしなかった。
三日、新羅は沙湌の金清平を遣わして政を報告し、併せて汲湌の金好儒、弟監大舎の金欽吉らを遣わして貢物を献上した。その送使の奈末の被珍奈、副使の奈末の好福は、清平らを筑紫まで送ってきた。
この月に粛慎の七人が、清平らに従って来日した。
十九日、京に近い諸国に詔して放生を行わせた。
二十日、全国に使者を遣わして金光明経と仁王経を説かせた。
二十三日、高麗が大使の後部主簿阿宇、副使の前部大兄徳富を遣わして、朝貢してきた。このため新羅は、大奈末の金揚原を遣わして、高麗の使者を筑紫に送ってきた。
この年、新城に都を造ろうとしてその地域の田畑は公私を問わず全て耕さなかったので荒廃した。
天武天皇六年春正月十七日、南門で弓の試合をした。
二月一日、物部連麻呂が新羅より帰国した。
この月、種子島の人々を飛鳥寺の西の槻の下で饗応した。
三月十九日、新羅の使者の清平以下十三人を京に召した。
夏四月十一日、天皇を謗ったかどで杙田史名倉を伊豆島に流した。
十四日、新羅の送使の被珍那らを筑紫で饗応した。彼らはそのまま筑紫から帰国の途についた。
五月一日、告朔の儀式は行わなかった。
三日、大博士で百済人の率丹に大山下の位を授け、食封として三十戸を与えた。この日、倭画師音檮に小山下の位を授け、食封二十戸を与えた。
七日、新羅人の阿湌朴刺破の従者三人と僧侶三人が血鹿島に漂着した。
二十八日、「諸国の神社の神税は三つに分けて一つを神に奉り、残りの二を神主たちに分け与えよ」と詔した。
この月、旱魃があった。京と畿内で雨乞いをした。
六月十四日、大地震があった。この月、東漢直の者らに次のように詔した。「お前たち一族は今までに七つの罪があった。それゆえに推古天皇の御代から天智天皇の御代に至るまでお前たちは常に警戒されてきた。今、朕の世になり、もしお前たちがまた罪を犯せば処罰するつもりだ。しかし、何も漢直の一族を絶やしたいわけではない。それゆえ、大恩を下して許す。今後、もし罪を犯す者があれば必ず処罰する」
秋七月三日、龍田の風神と広瀬の大忌神を祀った。
八月十五日、飛鳥寺で盛大な斎会を行い、一切経を読ませた。天皇はそのまま寺の南門に出御して三宝を拝礼した。このとき、親王、諸王、および群卿に詔して、各人につき一人の出家を許した。その出家は男女や長幼を問わず、皆願い通りに得度させ、大斎会に参加させた。
二十七日、金清平が帰国した。漂着した朴刺破らも清平らにつけて新羅に帰した。
二十八日、耽羅が王子の都羅を遣わして朝貢した。
九月三十日、浮浪者で、その本籍地に送還された者がまた戻った場合は本籍地と居住地に両方で課役を科す旨を詔した。
冬十月十四日、内小錦上の河辺臣百枝を民部卿とし、内大錦下の丹比公麻呂を摂津職大夫とした。
十一月一日、雨が降ったので告朔の儀式を行わなかった。筑紫太宰が赤烏を献上したので、太宰府の諸司の人々にそれぞれ位に応じて禄を賜った。且つ、赤烏を捕らえた当人には爵位五級を賜った。そしてその郡の郡司らには爵位を加増した。郡内の百姓たちには一年分の課役を免除した。この日、大赦を行った。
二十一日、新嘗祭を執り行った。
二十三日、百寮の有位の者に新穀を賜った。
二十七日、新嘗祭に従事した神官および国司たちに禄を賜った。
十二月一日、雪が降ったので告朔の儀式を行わなかった。
挿絵:ユカ
文章:水月
日本書紀「天武天皇(12)」登場人物紹介
<天武天皇>
第40代天皇。壬申の乱に勝利して即位した。
<大来皇女>
天皇の皇女。泊瀬斎宮から伊勢神宮に奉仕のため遷った。祭祀を通じて王権と神道を結ぶ象徴的な存在。