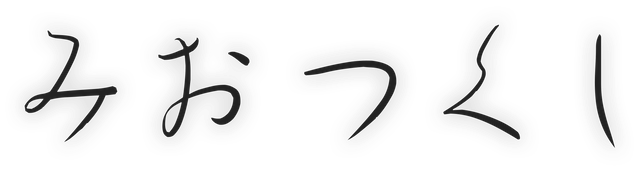倭で銀が初めて産出され、諸神に奉献。国内統制を進める中、外国使節が相次いで来朝し、祭祀・仏事・人材登用も盛んに行われた。
日本書紀「天武天皇(11)」
天武天皇三年春正月辛亥の朔、庚申の日(1月10日)。百済王・昌成が薨じた。小紫位を追贈した。
二月辛巳の朔、戊申の日(2月28日)。紀臣・阿閉麻呂が死んだ。天皇は深く悲しみ、壬申の乱での功績を思い、大紫位を追贈した。
三月庚戌の朔、丙辰の日(3月7日)。対馬国の国司守である忍海造大国が、「国で銀が初めて採れました」と報告し、すぐに献上した。このため、大国は小錦下の位を授けられた。
この銀こそが、倭国の地で最初に出土した銀である。そこで、すべての神々に奉献し、小錦以上の位の官人たちにも広く賜った。
秋八月戊寅の朔、庚辰の日(8月3日)。忍壁皇子を石上神宮へ遣わし、神宝を膏油(動植物由来の油。神宝を清めるために用いる)で磨かせた。

その日に天皇は詔を発して言った。
「これまで各家が神府(神社の倉)に納めていた宝物は、今すべてその子孫に返還せよ」
冬十月丁丑の朔、乙酉の日(10月9日)。大来皇女、泊瀬斎宮(泊瀬は奈良の初瀬)より伊勢神宮へ向かった。
天武天皇四年春正月丙午の朔(1月1日)。大学寮の学生たち、陰陽寮・外薬寮および舎衛女・墮羅女・百済王善光・新羅の仕丁などが、薬や珍しい献上品を携えて進上した。
丁未(1月2日)。皇子以下、百官が朝廷に参内し、拝礼した。
戊申(1月3日)。百寮の初位以上の者たちが薪を献上した。
庚戌(1月5日)。占星台の建設が始まった。
壬子(1月7日)。群臣に朝廷で宴を賜った。
壬戌(1月17日)。公卿・大夫および初位以上の百官たちが、西門の庭で弓の試合を行った。同日、大倭国から瑞鶏(めでたい鶏)が、東国からは白鷹が、近江国からは白鵄(白い鷲)が献上された。
戊辰(1月23日)。諸社に布帛を奉納する祭りを行った。
二月乙亥の朔(2月1日)・癸未(2月9日)。天皇の詔があり、大倭・河内・摂津・山背・播磨・淡路・丹波・但馬・近江・若狭・伊勢・美濃・尾張などの国に向けてこう命じた:「それぞれの地域の人民から、歌の得意な男女や、背丈の低い者(侏儒=こびと)・伎人(芸能に従事する人々)を選び出し、都に献上せよ」
丁亥(2月13日)。十市皇女・阿閉皇女が伊勢神宮に参拝した。
己丑(2月15日)。詔があった。「甲子年のときに諸氏に給された部曲(かきべ=私的配下)は、今後すべて廃止する。また、親王・諸王・臣下・諸寺などが授けられていた山・林・島・野・池も、これまでの分をすべて廃止する」
癸巳(2月19日)。詔して、「群臣百官および天下の人民は、悪事をしてはならぬ。もし犯す者あらば、事の軽重に応じて処罰せよ」と仰せられた。
丁酉(2月23日)。天皇は高安城(たかやすのき)に行幸した。
この月、新羅は、王子・忠元、大監・金比蘇、大監・金天沖、第監・朴武摩、第監・金洛水らを遣わし、貢物を献上した。また、使者の金風那・金孝福が、王子・忠元を筑紫まで送り届けた。
三月乙巳の朔丙午(3月2日)。土佐大社の神が、神刀一口を天皇に献上した。
戊午(3月4日)。筑紫において、金風那ら新羅使をもてなし、そのまま都へ帰還させた。
庚申(3月6日)。諸王のうち、四位の栗隈王を兵政官長(軍政の長)に、小錦上・大伴連御行を大輔に任じた。
この月、高麗が、大兄・富干、大兄・多武らを遣わし朝貢してきた。新羅からも、級飡・朴勤修、大奈末・金美賀らが貢物を献上してきた。
夏四月甲戌の朔戊寅(4月5日)。およそ2400人あまりの僧侶・尼僧を招いて、大規模な斎会(法要・供養)を営んだ。
辛巳(4月8日)。勅があり、小錦上・当摩公広麻呂、小錦下・久努臣麻呂の二人について、「参朝(朝廷への出仕)をさせてはならぬ」と命じた。
壬午(4月9日)。詔して言う。「諸国の貸税(貸付米などの徴収)は、今後は人民の実情を明らかにし、貧富の差を把握して三等に分類せよ。そして中戸(中程度の農家)以下には貸付を行うこと」
癸未(4月10日)。小紫・美濃王と小錦下・佐伯連広足を、龍田立野に遣わして風神を祀らせた。また、小錦中・間人連大蓋および大山中・曾禰連韓犬を広瀬河曲に遣わし、大忌神を祭らせた。
丁亥(4月14日)。小錦下・久努臣麻呂が、詔勅に反抗したため、その官位をすべて剥奪した。
庚寅(4月17日)。勅して、諸国に命じる。「今後、狩猟・漁労について以下を禁ずる。落とし穴や罠、機構を使った槍などを仕掛けてはならない。4月1日から9月30日までの間、比弥沙伎理・梁などの漁具を設けてはならない。牛・馬・犬・猿・鶏の肉を食べてはならない。
辛卯(4月18日)。三位・麻続王が罪を犯し、因播に流罪となった。その子一人は伊豆島へ、一人は血鹿島へ流された。
丙申(4月23日)。諸国から才芸のある者を選抜し、各々に禄を与えた。その内容に応じて等級が設けられた。
この月、新羅王子・忠元が難波に到着した。
六月癸酉の朔乙未(6月3日)。大分君恵尺が病で死にかけていた。天皇はこれに深く驚き、詔して言った。「お前・恵尺は、私的な利を捨てて公に尽くし、命を惜しまず、雄々しく大役に仕えてきた。私は常に慈しみ、愛していた。ゆえに、お前が死んでも、その子孫には厚く恩賞を与えよう」こうして、外小紫位を贈った。だが数日と経たぬうちに、恵尺は私宅にて薨じた。
秋七月癸卯の朔己酉(7月7日)、小錦上・大伴連国麻呂を大使に、小錦下・三宅吉士入石を副使として新羅へ派遣した。
八月壬申の朔(8月1日)、耽羅(済州島)からの調使・王子久麻伎が筑紫に到着した。
癸巳(8月2日)。強風が吹き、砂塵が舞い、家屋が倒壊した。
丙申(8月5日)。新羅王子・忠元、礼を終えて帰国の途につき、難波から船出した。
己亥(8月8日)。新羅・高麗の両国からの調使を筑紫で饗応し、禄をそれぞれに応じて賜った。
九月壬寅の朔戊辰(9月7日)。耽羅王・姑如が難波に到着した。
冬十月辛未朔癸酉(10月3日)。四方に使いを遣わし、一切経(仏教経典の総集)を求めさせた。
庚辰(10月10日)。群臣に酒宴を賜った。
丙戌(10月16日)。筑紫より唐人三十人が献上されたので、遠江国に送って定住させた。
庚寅(10月20日)。詔があった。「諸王以下、初位以上の者は、各自兵器を備えよ」
同日、相模国より「高倉郡の女性が三つ子の男子を産んだ」と報告があった。
十一月辛丑の朔癸卯(11月3日)。ある人物が宮中の東岳に登り、「妖しい言葉」を発して自ら腹を斬って死んだ。この夜、直(宮中の当直)を務めていた者すべてに、位一級が与えられた。
この月、大地震があった。
挿絵:さざちか
文章:くさぶき
日本書紀「天武天皇(11)」登場人物紹介
<天武天皇>
律令制整備の途上で、銀の献上・人材登用・仏事・肉食禁制など多面的に政策を進める。
<大来皇女>
天皇の皇女。泊瀬斎宮から伊勢神宮に奉仕のため遷った。祭祀を通じて王権と神道を結ぶ象徴的な存在。