義経と梶原景時が逆櫓の設置について口論を交わす。
元暦二年正月十日(1185年1月10日)、九郎大夫判官義経は後白河院の御所へ参上し、大蔵卿泰経朝臣を通じて院にこう奏上した。
「平家は神にも見放され申し、君(後白河院)にも見捨てられ申して、帝都を出、波の上に漂う落人となりました。ところがこの3年の間、平家を攻め落さず多くの国々の交通をふさがれたことは、残念に存じております。そのため義経といたしまては、鬼界が島・高麗・天竺(インド)・震旦(中国)までも、平家を攻め落さない限りは、王城(京)へ帰らない覚悟です」
と、頼もしそうに言ったので、後白河法皇はたいそう感嘆し、「十分用心し、昼夜兼行で勝負を決するように」と仰下した。
判官(義経)は宿所に帰り、東国の軍兵たちにこう言った。「義経は鎌倉殿(頼朝)の御代官として、院宣を拝承し、平家を追討するつもりだ。陸地は馬の足が行ける所まで、海は櫓や櫂の届く間は、攻めて行くであろう。少しでも二心ある者は、さっさとここから帰られよ」
さて八島では、月日が経つのも早く、正月も過ぎ、2月になった。春草が枯れて秋風に驚き、秋風が吹きやんで、やがて春草が芽生える。こうして春秋を送り迎えて、もはや3年になってしまった。
都には、東国から新手の軍兵が数万騎到着して、それが四国の方へ攻め下って来るとも噂が流れてくる。九州方面から臼杵・戸次・松浦党が同盟して渡ってくるとも、みんなが話し合っている。あれを聞き、これを聞くにつけても、ただ耳を驚かせ、肝をつぶすより他にない。女房たちは女院(建礼門院徳子)・二位殿(平時子)をはじめとして、寄り集まって、「またどんな悲しい目を見るのでしょう。どんな悲しいことを聞くのでしょう」と嘆き合い悲しみ合っていた。
新中納言知盛卿は、「東国や北国の者たちも、ずいぶん大恩を受けていたものだが、その恩を忘れて平家との従属関係を変え、頼朝や義仲らに従った。まして西国の者たちも、きっとそうだろうと思ったから、都でどうにでもなろうと思ったのを、自分一人だけのことでないので、気弱くあてもなく都をさまよい出て、今日はこういう情けない目を見ていて不甲斐ない」と言った。まことに道理と思われて哀れである。
同年2月3日、九郎大夫判官義経は、都を発って、摂津国渡辺から船揃えをし、八島にいよいよ押し寄せようとする。三河守範頼も同じ日に都を発って、摂津国神崎から兵船を揃えて、山陽道へ赴こうとする。
同月13日、伊勢大神宮、石清水八幡宮、賀茂・春日神社へ官幣使を派遣された。「天皇並びに三種の神器が無事に内裏にお帰りになるようにしてください」と、派遣された神祇官の役人やそれぞれの神社の神主が、本宮・本社でお祈りすべき由を、朝廷から仰下された。
同月16日、渡辺と神崎の2か所で、数日前から揃えていた船の纜(ともづな。船をつなぎとめる綱)をいよいよ解こうとした。ちょうどその時、北風が木を折るほど激しく吹いたので、大波のために船がさんざんに破損されて、船を出すことができなかった。修理のためにその日はそこに留まった。渡辺では大名と小名が寄り合って、「そもそも我々は、船での戦い方は訓練していない。どうしたらよかろう」と評議した。
梶原景時は「今度の合戦には、船に逆櫓を立てるつもりです」。判官は、「逆櫓とはなんだ」と尋ね、梶原は「馬を駆けさせるときは、左手へも右手へも回しやすいもの。船はすばやく押し戻すのが困難なもの。船尾と船首に櫓(やぐら)を交差して立て、脇楫(補助の舵)をつけて、どちらの方角へも容易に押すようにしたいものです」と答えた。
判官は「戦というものは、一歩も引くまいと思う時でさえ、戦況が悪ければ引くのが常である。初めから逃げる支度をしていては、なんのよいことがあろうか。門出にあたって不吉なことだ。逆櫓を立てようと返様櫓を立てようと、貴殿らの船には百挺でも千挺でも櫓をお立てなされ。義経は元の櫓で戦おう」と言うので、
梶原は「よい大将軍と申すのは、駆けるべきところは駆け、引くべきところは引いて、身の安全を保ち、敵を滅ぼすもの。それをもって、よい大将軍とするのです。攻勢一方で変えないのは、猪武者といって良くないよいことです」と申すと、
判官が「猪だか鹿だか知らないが、戦は一気に攻めに攻めて勝つのが気持ちのよいものだ」と言うと、侍たちは梶原に恐れて大きな声では笑わないが、目配せし花で嘲笑し合った。判官と梶原で、いよいよ同士討ちをするにちがいないと騒ぎ合った。
しだいに日が暮れて夜に入ったので、判官は「船が修理して新しくなったゆえ、各自一品の肴、一瓶の酒で祝うといい、殿方」といって、酒肴の用意をするような様子で、船に武具を入れ、兵粮米を積み、馬どもを船中に立てさせて、「急いで船を出せ」と言ったので、船頭や水夫は「この風は追い風ですが、普通以上の疾風です。沖はさぞかし吹いておりましょう。どうして船を出せましょうか」と言うと、
判官は大いに怒って、「野山の果てで死に、海川の底に溺れて死のうと、これはみな前世で行ったことの報いだ。海上に出て船で浮かんだとき、風が強いといってなんだというのか。向い風なのに渡ろうというなら、それは不都合だろうが、順風なのが多少強いからといって、これほど重大な時機になぜ渡りたくないなどと申すのだ。船を出さぬのなら、一人ずつ射殺せ」と命じる。
奥州の佐藤三郎兵衛嗣信、伊勢三郎義盛が一本ずつ矢をつがえ、進み出て、「どうしてあれこれ文句を申すのだ。君のご命令なのだから、さっさと船を出せ。船を出さぬのなら、一人ずつ射殺すぞ」と言ったので、船頭や水夫はこれを聞いて、「射殺されるのも船を出して死ぬのも同じことだ。風が強いのなら、ただ船を走らせて死んでしまえ、者ども」といって、200余艘の船の中で、ただ5艘が走り出た。残りの船は風に恐れたのか、梶原に恐れをなしたかで、みんな残っていた。
判官は「ほかの者が出ないからといって、留まるべきではない。波風の立たぬ普通のときは敵も用心するだろう。こんな大風大波で、誰も思いもよらないときに押し寄せてこそ、狙う敵を討てるのだ」と言った。5艘の船というのは、まず判官の船、田代冠者、後藤兵衛父子、金子兄弟、淀の江内忠俊といって船奉行の乗った船である。
判官は「各自の船に篝火をともすな。義経の船を親船として、その船尾と船首の篝火を目印について来い。火の数が多く見えれば、敵は恐れてきっと用心するだろう」といって、夜通し走ったので、3日かかるところをたった6時間ほどで渡った。2月16日(17日)の午前2時頃に渡辺・福島を出発して、翌日の午前6時頃に、阿波の地へ風に吹きつけられて到着した。
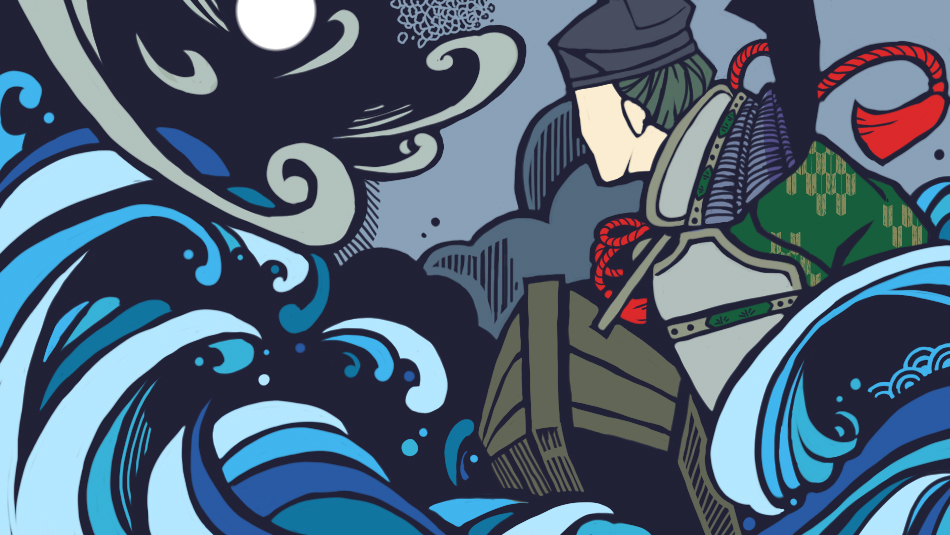
挿絵:黒嵜
文章:くさぶき
平家物語「逆櫓」登場人物紹介
<源義経>
源頼朝の弟。
<梶原景時>
源頼朝の臣下。相模国鎌倉郡梶原の住人。
